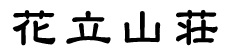各地から、桜の開花が届いています。
3月もあと1週間を残すのみになりました。そんな、春の到来とは裏腹に、お彼岸あけの丹沢は、ご覧のような積雪。

水分をたっぷり含んだ春の雪、溶けるのも早い。これからしばらくは、泥道対策が不可欠です。

いつもの土曜日と同じ天神尾根からの歩荷は、稜線の雪と芽吹きの準備を始めたブナを眺めながら、そして、大倉尾根との合流手前では、所によっては膝上までに達する雪との格闘と、変化のある一日でした。


花立山荘付近は、時折青空が顔を出すものの、気温の上昇のせいか、ガスに覆われた時間多く、天候の回復を期待してみえた登山者の期待を裏切ることとなっていました。


その分、翌朝は、麓からも一日中稜線が映えて、多くの登山者が、雪を纏った丹沢を満喫できたと思います。
ところで、いつものように歩荷のあとのトイレ清掃。気温の上昇とともに、バルブの凍結も解消され、不自由をおかけしていた水洗機能が復帰しました。これで、トイレ清掃も随分楽になります。それでも、水の不自由な山のトイレ、皆さんがいつでも気持ちよく使用できるよう、ご協力お願いします。


18/03/25 [日]
|
カテゴリー:季節の風景, 山の状況, 山小屋日誌
3月第2週の週末。丹沢の麓もすっかり春めいて、戸川公園の色彩の美しさに思わず足を止めてしまいます。

歩荷の起点としている本谷から戸沢に合流する渓流の水もぬるんでいる様子、春の訪れを感じます。


この週末、天気予報に反して、山は朝から、霙まじりの小雨。大倉尾根を登ってこられる登山者も口々に生憎の空模様が、恨めしそうでした。その代わりに、天神尾根の水墨画的な杉林の景色は、重い荷にあえぐ歩みに、少なからずの安らぎを与えてくれます。

山荘付近も、朝方の雪にちょっとした雪景色、氷の旗は寂しげでした。



さて、前回の、赤岳からのブログは如何でしたか。花立山荘は、余裕を見て、スタッフの登山スキルの向上のため夏の縦走から冬山まで訓練を兼ねた山行を実施しています。今回の山行では、冬山初めてのスタッフもいましたが、オーナの厳しい指導のもと無事、厳冬期のテント泊も赤岳登頂もできました。安全のため、時には大声が飛ぶこともありますが、登山は無事に帰るのが原則です。
無理をせず、装備、安全体制を整えてこれから始まる残雪期、夏山、秋山、そしてまた冬山と、四季それぞれの姿で迎えてくれる山を楽しみましょう。
個人的には、先週末の、三浦マラソン、昨日は、大山登山マラソンで今冬のマラソンシーズンも終了。なかなか、思うようにタイムも出ませんが、登山のトレーニングとしてのマラソンも欠かせません。
18/03/12 [月]
|
カテゴリー:スタッフの日常, 季節の風景, 山の状況
あっ、どうもはじめましてっ
スタッフ兼ブログ担当の山梨県甲府市民です。
花立山荘のブログ担当は2人おりまして、そのうちのアホの方とよく言われおります。
以後、お見知りおきくださいませ。
なんて。この期に及んで何言っとんのじゃ。
どうもみなさまご無沙汰しております。
人事異動が激しい時期にレアキャラ化するのがトレードマークになってまいりました(トレードマークの使い方をこのアフォに誰か教えてやって)。
いやいやだから下界じゃマトモ(棒読み)に働いてるっちゅーに。確かに小屋にいるときは目も当てられない醜態をさらしていますが。
忙しいを言い訳にしまくること2ヶ月、ここ最近全く小屋に顔が出せていないスタッフです。
準スタッフに降格しそうな予感。ヒョエー
さて、予想より遥かに早く春がやって来てしまいました。
丹沢に行けないストレスは近場の山で発散しているのですが、今日はとにかく暑かったですね。夏かよ!ってくらい。
長袖インナーとスパッツに半袖短パンと夏スタイルでもう汗だくだくでした。

普段は素通りする丸太の上で小休止。
花立山荘じゃかき氷も出たのでは?
かなぶん、とおるちゃんお疲れ様でーす。
じわり、じわりと丹沢にも夏が訪れようとしています。
バカ尾根を歩いているときのあの暑さ…思い出すだけでも体がだるくなりそうです。
夏を思うにはまだ早いので、ちょいと一旦涼しい話題をぶちこみましょうか!
暦を無視して氷の世界を堪能しましょう。
1月末に訪れた、美しい白銀の山行をお届けします。
(相変わらず無理矢理なつなげ方である)
2018.1.27-28
時は遡って1月末。
オーナー守さん、ボッカマシーン榎本先生、お味噌の達人でこさん、人材派遣業者めぐの4人で八ヶ岳へいってまいりました!

ドゥンッッッッッッ
いい写真~~~~~!(自画自賛)
美濃戸口に車を停め、林道をのこのこ歩きまずは美濃戸山荘前でパシャリ。
1日目は南沢から行者小屋を目指し、そこでテント泊です。

前の二人はペアルックと言わんばかりの赤

その後を歩くブログ担当ズは仲良く青
雪は深いものの行者小屋まではハイコングコースのような緩やかな道のりで、アイゼンをつけることなく直に雪を踏みしめて進んでいきます。

下界では目にすることのない雪の量に、細心の注意をはらいつつも時にははしゃぎながら1日目の目的地を目指します。
それにしても…

いや~いい天気~~~!
雲も出ていましたが日向はとっても温かく、行者小屋に着いたときにはジャケットを脱いでいても汗ばむほどでした。
小屋でテント泊の手続きを済ませたら、協力して今晩のお宿の準備です。

あ、あれ…エノモっちゃんまで赤くなっとるやないか…スタッフみごとにハブられたね…(泣いてないもん)
テントが完成したのは13時前。
宴会を始めるにはまだ早すぎる時間…ということでチームレッドはアイゼン講習へ、
ブログ担当ズはアイスキャンディの見物で赤岳鉱泉へ向かいました。
のこのこ、しゃくしゃくと雪の上を歩くこと30分…

やってるやってる~!いいなぁ。
いつ見ても圧巻です。
エノモト先生の解説にうんうん頷きながらアイスキャンディを見物し、女子トイレ行ってる隙にこのおっちゃんはちゃっかり若いねーちゃんをナンパし、そんなこんなで来た道をヒーコラヒーコラ歩いていると…
行きの時は素通りした、展望台の分岐で立ち止まり。
ベテラン・エノモト先生ですら行ったことのない展望台。
時間もたっぷりあるしどんなものか見てみようか、と大して期待せず10分弱登ってみると…

どわーーーーっ絶景やないか!!!
そこには八ヶ岳南部を見渡せる大パノラマが広がっていました!
エノモト先生ですらインスタ映えする威力。
個人的にこの山行で一番印象に残った景色でした。お見事!
小屋に戻ったのは15時前。
ちょうどアイゼン講習組も戻ってきました。
翌日も早いし…もうおっぱじめてもいいんじゃないの?
テントの中で炭酸の弾ける心地よい音色が響きました。
そして今宵のディナーは…

煮込みうど
いやいやいやまてまてまて!
素うどん!すうどんやんかこれ!
ちょ底!底から具出して具!ぐ!!!

オォ~~~~~
とってもおいちい煮込みうどんでした。

テントの中はいつもハプニングだらけ。
でもそれがとっても楽しいんですよね。
うどん、おつまみ、お酒をたいらげ…満足したご一行は18時前に就寝。
本番は翌日ですから。
久しぶりの雪に戸惑ったであろう体をしっかりと労りました。

翌朝。
寒い。けど、想像してきたよりは寒くない。

これから顔を出さんとする朝日の訪れを感じながら、少し緊張感を漂わせチーム花立はテントを後にします。
文三郎尾根から目指すは、八ヶ岳最高峰。
夏ですら登ったことのない赤岳の頂に、まだ不馴れなアイゼンを装着して進んでいきました。

しかし険しい。止まることは許されない。
風は強くなり、ただでさえ重い足取りに容赦なく負荷をかける。
パンクしそうなふくらはぎに鞭を打ち、唸りながら急勾配を登っていきます。

曇ればそこはモノクロの世界。
大袈裟ですが、生きた心地がしませんでした。
ただひたすらに足を動かしつづけ、写真を撮る余裕もなく、時間を気にする余裕もなく。
気付いたら、目指していた場所に立っていました。

完全に目が死んでいる…

山頂からは遠くそびえる富士山も。
しかしここで先に力尽きたのはスタッフではなくスタッフ携帯。
あまりの寒さに20%残っていた電池が一瞬にして0になりました。無念。
前日にエノモッちゃんがナンパした美女ともこちらで再会しました。
あの65歳、私より若く見えるのは気のせいだろうか…。
ナンパおやじを罰ゲームで写真係に認定したところで、北峰で集合写真です!

白馬山行を彷彿させる足の痛みだった…
さ、下りは地蔵尾根です!
相変わらず風は強かったですが、山頂で食べた一口あんぱんでHPほぼフル回復したスタッフ、上機嫌でくだっていきます。
腹減ってただけじゃねーか。

ふてぶてしいまでに余裕をかます
エノモト先生の山岳講座を聞きながら、北アルプスや中央アルプスの姿を目に焼き付け、無事下山です。
テントを回収し、美濃戸口に戻ったのは13時頃。
守さんが夜に予定アリのため、寄り道せず帰路につきました。
帰りの車中でダメ元でケータイの電源を長押しすると…あら復活するじゃないの。
複数ラインがたまっていると思ったら、そこには見覚えのある花立ダジャレオヤジからのメッセージ。
内容は…

ゴム手袋が凍って立ったんだとさ。
どーーーーーでもええーーーーーー
それにしても自分の体力の無さ、足の弱さを痛感した山行でした。
まだまだ雪山の経験値は無いに等しく、守さん榎本さんがいなければなにもできない。
冬は夏に向けて、夏は冬に向けて、年中トレーニングは怠っては行けないと身をもって学びました。

厳しくも白銀の世界は美しい!
危険が多くてもチャレンジしたくなる。
雪山には不思議な魅力がたくさん詰まっていました。
18/03/04 [日]
|
カテゴリー:スタッフの日常, 季節の風景